「美白」「whitening」の表現が消えるかも?
- reethihandhuvaru
- 2020年9月10日
- 読了時間: 3分
外資系の化粧品会社が、スキンケア商品やブランド名から「美白」もしくは「whitening」表現を外す動きが広がっているそうです。
何故、そんなことになっているのでしょうか?

「美白」や「whitening」の表現を外すとしたら・・・。
美白系スキンケア商品の表現は「雪」や「氷」「水」のイメージやコピーを使うのでしょうか?
洗顔料や拭き取り用化粧水に使用する「透明感」的な、「airy(エアリィ)」な表現を使うのでしょうか?
「澄み切る」とか「濁りのない」とか・・・。
どんなコピーを使用するのか、コピーライターの腕が試されますね。
そして、提案されたコピーをどう選ぶのか?メーカーのセンスも問われます。
ちょっと、その辺りは楽しみです。
さて。
この動きのきっかけは、Black lives matter。
特に今年アメリカで起きた、黒人暴行死事件(ジョージ・フロイド殺害事件)が発端です。
事件の底には根深い人種差別問題があり、以前から同様の事件が後を絶ちませんでした。
ミネソタ州ミネアポリスで起きた2020年5月25日のこの事件をきっかけに、大きなうねりとなって、全世界に抗議が広がっています。
そして。
化粧品の美白やwhitening表現は、人種差別を助長しているのではないか?
表現を改めるべきではないか?
・・・と、問題提起されているのです。
White(ホワイト=肌色)が、より優れていると思わせる表現になっていると。
「美白商品」は、そもそもアジア圏以外では訴求はありませんでした。
白人が優れているとか、そういう意識で出来上がった商品では無いと思うのですが・・・。
アジア圏は、程々に日焼けして程々にシミが出来る肌色の人たちが沢山住んでいたので、シミは多くの女性たちの悩みのタネでした。
日焼けによる色ムラや肌荒れなども。
「美白」は、その悩みに対応している表現だったのです。
アジア圏以外の人達の肌は、シミという悩みを持ちにくい肌でした。
メラニンが少なくて、日焼けをしたら火傷状態(サンバーン)にはなりやすいけれど、シミになりにくい人たち、もしくは紫外線から肌を守るためにメラニンが元々多くて、シミになったりしない人たちが多かった。
移民のアジア系以外、需要が無かったのです。
ですから、欧米では商品開発自体、なされていませんでした。
でも・・・アジアの人口は魅力的ですね?
大きな市場です。
人口も経済も落ち込んできている欧米よりも、爆発的な人口と経済発展が進むアジアの商圏を見逃す筈もなく、次々に商品が開発されて、アジア圏に投入されました。
かなり、儲けた(下世話ですみません)と思われます。
外資系化粧品というだけで、おしゃれだと感じる人や妄信的に素晴らしいと思っていらっしゃる方も多いので。
・・・とは言え。
いまだに、日本ではティーンエイジャーのメイク思考が、プリンセス系&ドール系なことや、ハーフ系美女が人気の日本の芸能界などを見ると。
根っこには白人礼賛(というか、コンプレックス?)があるのかもしれません。
そして、やっぱりこの島国でも、あらゆる差別問題がある。
今の所、日本の化粧品メーカーは、外資とは足並みを揃える気は無いようです。
「美白」の日本の化粧品の成り立ちから考えれば、Black lives matter 問題とは、別軸だと言いたくなるのも解ります。
どの辺りに、落ち着くでしょうか?
色彩の世界では、白も黒も同じ無彩色。
どちらも美しい色です。
色をつけて見る(フィルターをかける)のは人間です。
肌の色は環境に合わせて生物であるヒトが対応した結果なだけ。
優も劣も無いのになぁ。
相手の立場に自分が置かれたらどうなのか?
・・・想像力が無い大人にはなりたく無い(もう十分大人なんだけど)なぁ。
*****
芙蓉の花です。
美女を表す花と言われておりますが、昔は蓮の花のことだったそうな。
今は、蓮のことを芙蓉と区別するために水芙蓉と表現するそうです。
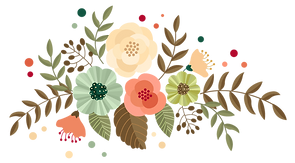



コメント